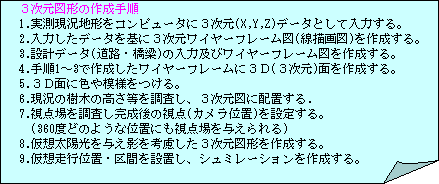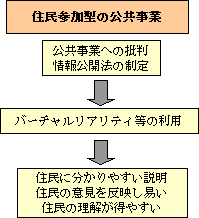

(クリックすると拡大表示されます)
しかし、従来の平面図や横断図等を使った地域住民への説明はイメージが伝わりにくく、理解しにくい面があるため、住民の描くイメージと合わなかったり、行政側の説明もうまく伝わらないことがあります。そのため近年、視覚性・現実性に優れたCGアニメが使われるようになってきました。
CGアニメは、位置・形状・色や周辺の景観をバーチャルリアリティでシュミレーションすることによって完成後を仮想体験することができますが、コスト面で負担が大きいため実際に計画・設計作業に活用しているところはまだ少ない状態です。しかし、近年インターネットの話題に象徴されるようにコンピュータ化へ向けての注目度は高まっており、21世紀のマルチメディア時代、情報化社会、ボーダレスな世界においてもコンピュータの役割は無限の可能性を秘めているように感じます。
当社ではAutoCAD,3DStudio等の一般的なソフトを使って3次元図形を作成することによりコスト面での負担を軽減、道路や橋梁の完成後を想定していろいろな視点場よりどのように見えるか、どのような形状になるかなど周辺環境への影響と調和について分かりやすい3次元図形を作成しています。
※AutoCAD、3DStudioは米国Autodesk,Inc.の米国及びその他の国における登録商標です。